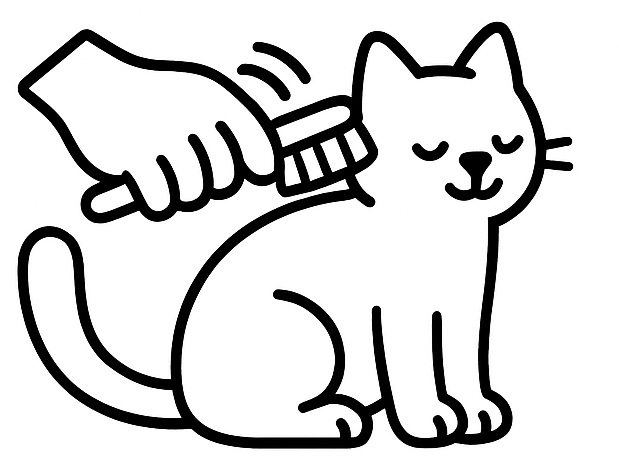目次(クリックすると各項へジャンプします)
01 皮膚糸状菌とは
02 症状
03 診断
04 治療
05 環境のクリーニング
06 同居の家族への対応
07 予後
08 参考文献
01 皮膚糸状菌とは
皮膚糸状菌は、人の水虫に近い仲間のカビで、皮膚や毛、爪に感染して皮膚病を起こします。犬や猫、ウサギ、ハリネズミ、モルモット、チンチラ、牛など、いろいろな動物に感染します。皮膚糸状菌には何種類かあって、動物種によって感染しやすい糸状菌の種類が異なります。
感染は病気の動物に直接触れるだけでなく、環境中に落ちた毛やカビの胞子に触れることで起こります。この胞子はとても丈夫で、環境中で1年間くらいは感染力を保つといわれています。そのため、掃除や消毒が不十分だと、せっかく治ってもまた環境中の菌から感染してしまうことがあります。
皮膚糸状菌は感染力は強いものの生命を脅かすことはなく、治療で完治できます。ただし動物から人にうつるため、注意が必要です。
02 症状
03 診断
皮膚糸状菌の診断は、いくつかの検査方法を組み合わせて行い、症状とあわせて総合的に判断します。1つの検査だけで決めるのではなく、複数の方法で確かめることが大切です。
ウッド灯(ウッドランプ)検査
特別な紫外線ライトで毛や皮膚を照らし、皮膚糸状菌の1種が作る物質を光らせて確認します。感染している毛は、青りんごのような色に光ります。
げっ歯類に感染する皮膚糸状菌など、ウッド灯で光らないものもいます。
直接鏡検
毛やフケ、かさぶたを顕微鏡で観察し、菌がついているかを調べます。感染した毛はふくらんで輪郭がぼやけ、色が薄くなり、毛の表面に胞子がびっしりと付いているのが見えます。
培養検査
病変部の毛やフケ、かさぶた、または歯ブラシで全身をブラッシングしたものを培地に植え、菌を育てます。皮膚糸状菌が育つと色が変わる特別な培地を使うこともあります。真菌は育つのが遅いため、結果が出るまで1〜3週間かかります。
皮膚糸状菌症の原因菌として一番多い、Microsprum canisのコロニー。

PCR検査
毛やフケ、かさぶたに含まれる皮膚糸状菌の遺伝子を調べる方法です。早く結果が出て感度も高いですが、治療によって死んだ菌が残っていても陽性になることがあるため、治療終了の判断には向きません。
04 治療
皮膚糸状菌の治療は、
①動物の治療
②生活環境のクリーニング
この2つを同時に行うことが大切です。動物だけ治しても、環境に残った胞子から再び感染してしまうからです。
動物の治療
飲み薬:イトラコナゾールやテルビナフィンなどの抗真菌薬を使います。
シャンプー:抗真菌薬入りのシャンプーで全身を洗い、毛や皮膚についた菌を除去します。
塗り薬:皮膚病がごく小さい場合は、抗真菌薬の塗り薬で治療することもあります。
治療の終わりの判断
皮膚病変が消失し、真菌培養で陰性になったことを確認してから終了します。見た目でよくなったからと自己判断で中止すると、まだ菌が残っていて再発することがあります。
治療期間は、1~2か月かかります。人の水虫と同様、根気よく治療する必要があります。
05 環境のクリーニング
皮膚糸状菌の環境対策は、家の中に落ちた毛やカビを減らして、再感染や、他の家族への感染を防ぐことが目的です。流れとしては、
まず掃除で物理的にカビを減らす→その後に効果のある消毒剤で消毒する
という順番で行います。
動物からはしばらく菌が出続けるため、1回だけでなく、何度も繰り返すことが大切です。
掃除
カーペット・ソファ・フローリングなどは掃除機をかけます。
※へパフィルター付きの掃除機だと、吸い込んだカビの胞子が外に出にくくなります。
汚れが多い場所は、水拭きもしてきれいにします。
布製品はカーペットクリーナー(リンサークリーナー)で洗ったり、クリーニングに出すのも有効です。
洗濯
ソファカバー、クッション、カーテン、ペットベッドなど洗える物は洗濯します。
通常の洗剤を使い、洗濯機の一番長いコースで2回洗うと、消毒薬を使わなくても菌を除くことができます。温水にする必要はありません。
消毒
汚れが残っていると消毒効果が下がるので、必ず掃除の後に行います。
消毒薬は対象が濡れるまでたっぷりかけ、10分ほど置いてからふき取ります。
カーペットやソファなどふき取りにくい物は、カーペットクリーナーで洗いながら吸い取る方法もあります。
どの消毒薬も変色の恐れがあるため、まずは目立たない場所で試しましょう。
皮膚糸状菌に効果的な消毒薬
次亜塩素酸ナトリウム
濃度6%前後の次亜塩素酸ナトリウム(家庭用のハイターなど)を1:10〜1:100に薄めて使います。
漂白作用・強い臭い・他の薬品との混合で有害ガスが出る危険があるため注意が必要です。
希釈後は効果が落ちるので、不透明容器に入れて1週間以内に使い切ります。
加速化過酸化水素(AHP)
過酸化水素に界面活性剤などを加えたもので、次亜塩素酸ナトリウムと同じくらいの効果が確認されています。
有機物があっても効きやすく、臭いや変色も少なめ、残留もほとんどありません。
国内では動物用(Rescue™)の入手は難しいですが、同成分の一般製品(オキシヴィル、ハイプロックスアクセルなど)が入手可能です。
濃縮タイプとそのまま使えるタイプがあり、使い方は製品表示に従います。
環境中の皮膚糸状菌を調べたい方はこちら↓
06 同居の家族への対応
同じ家に他の動物がいる場合は、みんなの真菌検査をします。もし感染している動物がいたら、一緒に治療します。陰性の場合は、環境クリーニングをしながら、体に付いた菌を落とすためにシャンプーを行うなどして感染を防ぎます。
人の肌にも赤くて丸い発疹がないか、ときどきチェックしてください。できやすい場所は、顔・首・胸元・腕の内側など、ペットとよく触れるやわらかい部分です。特にお子さんやご高齢の方、病気で体が弱っている方は感染しやすく注意が必要です。
人の皮膚糸状菌症でも、抗真菌薬による適切な治療を受ければ比較的早く治ります。大切なのは、自己判断でかゆみ止めなどを塗らず、必ず皮膚科を受診することです。その際、ペットが皮膚糸状菌症になっていることを必ず皮膚科医に伝えてください。
診断が遅れ長期間ステロイドを使ってしまうと、特にお子さんでは重症化し、まれに脱毛の後遺症が残ることがあります(ケルスス禿瘡)。
07 予後
皮膚糸状菌症は、ほとんどの場合場完治する病気で、軽い場合は自然に治ることもあります。そのため、治療の目的は環境中の菌を減らし、ほかの動物や人への感染を防ぐことにもあります。
症状がはっきり出ている場合は治療に数か月かかることがありますが、途中でやめずにきちんと治療を続ければ、ほとんどのケースで治ります。
ただし、ペルシャ猫では治りにくかったり、症状も強くなることがあります。また、多頭飼いやシェルターでは、環境や他の動物からの再感染が繰り返されるためしつこく蔓延することがあります。このようなときは全頭検査を行い、隔離・治療・環境クリーニングを徹底し、根気強く対応していく必要があります。
08 参考文献
(1) 世界獣医皮膚科学会(World Association for Veterinary Dermatology 、WAVD) によるイヌとネコの皮膚糸状菌症のガイドライン(2017)
Diagnosis and treatment of dermatophytosis in dogsand cats.Clinical Consensus Guidelines of the World Association for VeterinaryDermatology
(2) 欧州猫疾患諮問委員会(European Advisory Board on Cat Diseases、ABCD)によるネコの皮膚糸状菌症のガイドライン(2013)
GUIDELINE for Dermatophytosis, ringworm in cats — ABCD cats & vets
(3) 犬・猫の皮膚糸状菌症に対する治療指針 皮膚糸状菌症 ガイドライン 日本獣医皮膚科学会(2018)